1章、第2節です。先の第1節にてティム氏もつくってきた「オープン・ソフトウェア」の流れ。それがこれからどのようになっていくのかを描きます。
専門的な話が多い気がします。まず、ポイントを5点。
○ネットワークがつながりあう世界を、ティム氏は「 Global Brain 」(グローバル・ブレーン)と例えている。
○大切なのは「集合知」である。←三人寄れば文殊の知恵か!?
○「ベクトル」(線の角度や大きさ、方向)で情報を受け入れる。未来は予測不可能なベクトルの交差点でなりたっているだろう。よって、点を打っていくような情報の捉え方よりも、(難しいが)ベクトルを受け入れる感性が大切になってくる。新しい情報はいつも複数のシナリオを有することも気にしたい。
○センサー技術の発達で、Global brain にとどまらず、Global body になるかもしれない。ただ、それら情報をつかうのは、われわれ人間の行動であることを忘れてはならない。
○1998年~2005年にかけて、アマゾンやグーグルから未来の地図を得てきた。そして、これからのトレンド地図を描くのは、Uber社 とそのライバルである Lyft社である。
以下、概要を。
ティム氏が見てきたこと
オープン・ソフトウェアという用語を共通で使う足がかりをつけた。そしてリナックス(OS)の快進撃。と思うや否や、アマゾンやグーグルという新興勢が躍り出てきた。
彼らはソフトウェア企業というより「データ」と「ひと」の集まり方が優れている。← 興味深い見方です
現在の状況につながるパズルのピースが揃ってきた。そして、最後のピースは2003年…
WEB 2.0
ウェブ2.0はインターネットが次世代のプラットフォームになる。そんな流れを印象づけるものであった。インターネットブラウザの競争もあった。ただ、これらはパッケージソフトウェアの競争に過ぎなかった。グーグルは完成版であるパッケージソフトウェアを提供していない。かれらはずっと開発をし続ける(ベータ版)。サービスし続けることを選んでいる。
iTunesでアプリケーションはひと区切り
アップル社の音楽配信ソフトウェア iTunes。このソフトウェアは3つの利用方法がある。ひとつはパソコンで。もうひとつはクラウドでどこでも楽しめる。そして、最後はモバイルで。この3つが組み合わさったアプリケーションである。
そして、これからのアプリケーションはもっと複雑になる。モデルはUber社である。彼らはGPSを活用して交通情報を利用している。
集合知を活かす
Global brain から、Global collaborationへ。グーグルのサービスはユーザの活動が、その検索サービスのランキングに用いられる。そしてアマゾンは購買者がレビュアーも兼ねる。
自動運転技術も、ユーザ(運転者)からの情報が欠かせない。その点で、テスラ社、そしてUber社はチャレンジングな取り組みをしている。
一体、”誰が”データを有しているのだろう。そしてどのようにデータを有するのかのみならず、どのようにデータに意味を持たせるか。これも企業にとっては大切な視点になってくる。
ベクトルで考える
プロット、すなわち点をひとつずつ打ちデータを受け入れるのではなく、未知数のままの情報をそのまま受け入れる姿勢をもってはどうか。
未来は、ベクトル(方向性をもつ力)がいくつも交錯する世の中になっているだろう。複数のシナリオが考えられ、未来だって複数ある。
P.29
私は未来を予測してはこなかった。テクノロジーやビジネスの大枠をつくるであろう力を見つけ、それを現在の地図に落とし込んで来ただけなのだ
次世代の企業
Uber社 とそのライバルである Lyft社を見ていく。Global brain になろうとも、そのデータを活用するのはわれわれ人間の行動なのだ。
※WTF? /// 読み解きにあたって
https://www.storyinnovation.me/2019/01/15/wtf-in-the-beginning/
※「WTF?」に関わるまとめ読みは下記より
https://www.storyinnovation.me/tag/wtf/
![WTF?: What's the Future and Why It's Up to Us[Kindle版] WTF?: What's the Future and Why It's Up to Us[Kindle版]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51HtRSB-fSL.jpg)
WTF?: What’s the Future and Why It’s Up to Us[Kindle版]
- 作者:Tim O’Reilly
- 出版社:Cornerstone Digital
- 発売日: 2017-10-19


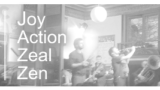
コメント