韻に耳を澄ます
歴史はただ繰り返されるのではない、韻を踏んでいるのだ
技術史になるので詳述は避けます(そもそも私も自身も詳しくない)。”オープンソース” の歴史を振り返り、その価値は誰のためのものかを問いかけます。
歴史は韻を踏む
オープンソースにまつわる地図はいろいろありました。それぞれの時代で、韻を踏んでリズムをとっていたようです。
いまでいうと、パソコンとスマホがそれぞれの地図を描いているのでしょう。過去にさかのぼると、AT&Tがユニクスを生み出した。それがコンピュータのオープンソースへとつながっていきます。ユニクスの権利を求める戦いがあり、より自由(オープン)をもとめてリナックスが生まれた。
コンピュータでいうとIBM、ウィンドウズ。企業から個人へ、ハードからソフトへの流れ。そして、ウェブサービスで言うと Perl というプログラムをオープン化した ラリー・ウォールを挙げています。
歴史は韻を踏んで、パズルのピースが浮かび上がる。
そのピースは、偶然に起こっているわけではなく、個人個人の決断によって引き起こされている。そして、そこに至る個人はまず 楽しさ(fun)が大切なのだ。
そうティム氏は考えています。
協働と、不完全でもよい
たとえばウィキペディア。フリーで提供されるオンライン辞書ですが、編集は自由意思を持つユーザたちが行うことで成り立っています。
「協働」で辞書の編集を行うこと。そして、「不完全でもよい」ので情報が更新されること(真偽は別のユーザが協働で編集を重ねる)。
以上、ふたつの文化がオープンソースを支えるとされます。
書いてしまうと当たり前なのですが、いざ自分が手掛ける仕事でこの考えはどこまで許容できるでしょうか。また、自分のまわりのパートナーがこのようなスタンスだった場合、それらはどこまで許容できるのでしょうか。
仮に、このオープンソース文化で世界がまわりはじめているならば、改めて自分自身の許容度を確かめることが大切でしょう。
そして、オープンソースからのフィードバックをいかに受け、次につなげていくか(ダブルループ学習など)も課題となります。
その価値は誰のために
英語の “Free” という単語にはふたつの意味があるようだ。それは『 libre(障害物がなく)自由 』と『 gratis(無料の/で)』だ
とはリナックスを開発したリーナス・トーバルズ氏の言葉。
焦点は誰がその free の価値を享受できるか。
ティム氏はこのように結びます。
P.17
How can a business create more value for society than it captures for itself?
ビジネスにおいて – オープン(協働、進行形)から – 生み出される価値は、どのように社会に生かすことができるのだろうか。会社のためだけではなく。
ティム氏の視点を学ぶ Part 1。
視野の広がる言葉と思います。
ひとつの視点として押さえておきたいですね。
※WTF? /// 読み解きにあたって
https://www.storyinnovation.me/2019/01/15/wtf-in-the-beginning/
※「WTF?」に関わるまとめ読みは下記より
https://www.storyinnovation.me/tag/wtf/
![WTF?: What's the Future and Why It's Up to Us[Kindle版] WTF?: What's the Future and Why It's Up to Us[Kindle版]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51HtRSB-fSL.jpg)
WTF?: What’s the Future and Why It’s Up to Us[Kindle版]
- 作者:Tim O’Reilly
- 出版社:Cornerstone Digital
- 発売日: 2017-10-19


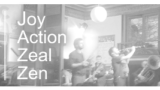
コメント